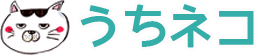猫の飼い主であれば一度は耳にしたことがある「去勢手術」。オス猫にとっては、望まない繁殖を防ぐだけでなく、発情によるストレスや問題行動(スプレー行為や攻撃性の増加など)を抑えるためにも、重要な処置です。
しかし、いざ去勢手術を済ませたにもかかわらず、「まるで発情期のように鳴き続ける」「夜中に大きな声で鳴くようになった」などの声を耳にすることがあります。これは一体どういうことなのでしょうか?
今回は、「去勢したのに発情期のような鳴き方をする猫」に関して、その原因と対策について詳しく解説します。
そもそも去勢とは?その目的と基本知識
オス猫の去勢手術とは、精巣(睾丸)を摘出する手術のことを指します。通常、生後6か月頃から手術が可能となり、動物病院で日帰りまたは一泊程度の入院で済む簡単な処置です。
主な目的は以下の通りです:
- 望まない繁殖を防ぐ
- 発情によるストレスや行動問題を抑える
- スプレー行動(尿マーキング)の減少
- 他のオス猫との喧嘩の減少
- 前立腺疾患や精巣腫瘍の予防
このように、去勢手術にはさまざまなメリットがあるのですが、手術後もなお発情期のような行動が見られる場合、「去勢が失敗したのでは?」と不安になる飼い主も少なくありません。
去勢手術が「失敗する」ことはあるのか?
基本的に、動物病院で適切に実施された去勢手術が失敗する可能性は極めて低いとされています。ただし、まれに以下のようなケースが存在します。
1. 側副精巣(未摘出の精巣)が体内に残っている場合
非常にまれなケースですが、猫によっては精巣が陰嚢内に降りてこず、お腹の中に残ったままの状態(潜在精巣、または停留精巣)で成長することがあります。外科的に確認されず、片方の精巣のみが摘出された場合、体内に残った精巣がホルモンを分泌し続けるため、発情行動が継続してしまうことがあります。
2. 体内に残存するテストステロンの影響
去勢手術後も、一時的に体内に残っていた性ホルモン(テストステロン)が数週間から数か月間作用することがあります。この影響で、手術後しばらくは発情に似た行動が続くことがあります。ただし、これは時間が経てば自然に収まるのが一般的です。
3. 実は手術を受けていなかった?
まれに、譲渡や保護された猫で「去勢済」と言われていたものの、実際には手術が施されていなかったというケースもあります。外見だけでは判断できない場合もあるため、動物病院で診断してもらうことが大切です。
発情期のような鳴き方をする他の原因
去勢がしっかり行われていたとしても、発情期のような鳴き方をすることがあります。その原因は、性ホルモンだけでなく、環境や心理的な要素が関わっていることが多いです。
1. 環境的ストレス
猫はとても繊細な動物です。環境の変化(引っ越し・家具の配置替え・新しい家族の追加など)や、騒音、隣家のペットの鳴き声などがストレスとなり、不安から鳴き続けることがあります。これは「発情鳴き」に似たパターンになることもあります。
2. 分離不安
飼い主とのスキンシップが少ない、または突然の留守番時間の増加によって不安を感じている猫は、注目を引くために大きな声で鳴くことがあります。特に夜間に鳴く場合は、飼い主に「かまってほしい」というサインの可能性が高いです。
3. 近隣の発情中のメス猫の影響
完全室内飼いであっても、近隣に発情中のメス猫がいる場合、そのフェロモンや鳴き声に反応してオス猫が興奮状態になることがあります。去勢していても、本能的な反応が残る場合があるのです。
鳴き方の特徴から分かる猫の心理状態
猫の鳴き声には、感情や要求が反映されています。「発情期のような鳴き方」と言っても、実はそうではない場合も多いです。以下のポイントに注目してみましょう:
- 低く、長くうなるような声:ストレスや警戒心
- 高く甲高い声で鳴く:発情に近い行動や不安
- 連続的でリズミカルな鳴き方:注目を引きたい、かまってほしい
- 夜間に鳴く・ドアの前で鳴く:外に出たがっているサイン
これらの情報をもとに、「本当に発情行動なのか、それとも別の要因か」を見極めることが重要です。
対策方法:どうすれば静かに落ち着いてくれるのか?
鳴き方の原因がわかったら、それに合わせて対策を講じることが大切です。
1. 動物病院での再確認を行う
まず第一に、信頼できる動物病院で「去勢が完全に行われていたかどうか」を確認してもらいましょう。超音波検査やホルモン検査で、体内に精巣が残っていないか確認することができます。
2. ストレス軽減の工夫
猫が安心できる環境作りを心がけましょう。
- 落ち着ける場所(キャットタワー・箱・個室)を用意する
- 環境音を抑える(テレビ・音楽・外の騒音など)
- フェロモン製品(Feliwayなど)を活用する
- 日々のルーティンを崩さない
3. 運動量を増やす
猫が退屈していると、無駄鳴きが増える傾向があります。毎日5~10分でも良いので、じゃらしや知育玩具で遊んであげましょう。
4. 夜間対策
夜間に鳴く場合、無視するのも一つの方法です。反応すると「鳴けばかまってもらえる」と学習してしまいます。夜は静かな環境と、寝る前にしっかり遊んで疲れさせることがポイントです。
まとめ
去勢後にも発情期のような鳴き方をする猫がいるのは珍しいことではありません。しかし、その原因は「手術の失敗」だけではなく、ストレス・環境・体内ホルモンの残存など、さまざまな要素が関係しています。
まずは冷静に猫の行動を観察し、必要に応じて動物病院で診察を受けましょう。そして、猫にとって快適で安心できる環境を整えることが、問題解決への第一歩です。
猫の行動には理由があるものです。根気よく向き合って、信頼関係を深めながら一緒に暮らしていきましょう。