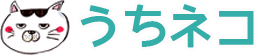猫を飼っている方なら、一度は愛猫が吐いている場面を目にしたことがあるのではないでしょうか。床に毛玉のようなものを吐き出したり、透明な液体を嘔吐したりする猫の姿に、驚いたり不安になった経験のある方も多いでしょう。
実は、猫は比較的吐きやすい動物です。人間であれば嘔吐は明らかに体調不良のサインと考えられますが、猫の場合は必ずしもそうとは限りません。しかし、頻繁に吐く場合や、吐く内容・タイミングによっては、重大な病気のサインであることもあります。
この記事では、猫が吐く原因とその見分け方、危険な兆候、そして飼い主ができる対処法について詳しく解説していきます。
猫が吐くのは普通のこと?
まず大前提として、猫が吐く行為は珍しいことではありません。猫は本能的に体調を自己管理する能力があり、胃の中の不要なものを排出するために吐くことがあります。特に以下のようなケースは、必ずしも病気とは言い切れません。
- 毛玉の排出:猫は毛づくろいを頻繁に行うため、毛を飲み込んでしまいます。その毛が胃に溜まりすぎると、吐き出して排出しようとします。
- 空腹時の嘔吐:朝方や長時間食事をしていないときに、胃液を吐くことがあります。透明〜黄色っぽい液体を吐くことが多いです。
- 早食いによる嘔吐:フードを一気に食べてしまうと、まだ消化されていない状態で吐き戻してしまうことがあります。
このような場合は一過性のもので、猫自身が元気で食欲もあるようであれば、あまり神経質になる必要はありません。
猫が吐く原因とは?
では、猫が吐く原因にはどのようなものがあるのでしょうか?以下に主な原因を詳しく見ていきましょう。
1. 毛玉(ヘアボール)
猫が吐く最も一般的な理由のひとつが「毛玉」です。特に長毛種の猫は、毛づくろいの際に大量の毛を飲み込んでしまうため、毛玉ができやすい傾向があります。毛玉は胃の中で消化されず、一定量に達すると嘔吐によって体外に排出されます。
対策:定期的なブラッシングや、毛玉ケア用のキャットフードを与えることで、毛玉の形成を予防できます。
2. 食べすぎ・早食い
ご飯を一気に食べてしまう猫は、消化が追いつかずに嘔吐することがあります。特に、吐いたものの中に未消化のフードがそのまま残っている場合は、早食いが原因の可能性が高いです。
対策:早食い防止用の食器や、1回の食事量を減らして回数を増やすなどの工夫が効果的です。
3. 食事内容の変化
急にフードを変更すると、猫の胃腸が対応できず、嘔吐してしまうことがあります。フードの変更は数日かけて徐々に行うことが大切です。
対策:新しいフードを少しずつ混ぜて、徐々に切り替えるようにしましょう。
4. 空腹による胃液の逆流
空腹時間が長くなると、胃液だけを吐くことがあります。胃液は透明または黄色っぽい液体です。
対策:1日数回に分けて食事を与えることで、空腹時間を短くすることができます。
注意が必要な嘔吐のパターン
上記のような生理的な嘔吐とは異なり、次のような場合は病気のサインである可能性があるため、特に注意が必要です。
1. 頻繁に吐く(1日に何度も、数日間続く)
嘔吐が1回きりではなく、何度も続くようであれば、消化器系の疾患や中毒の可能性があります。
2. 血が混じっている
血が混じった嘔吐物は、胃や食道に何らかの損傷がある可能性を示唆しています。
3. 吐いたあと元気がない・食欲がない
嘔吐とともに食欲不振や元気のなさが見られる場合は、体調不良のサインです。
4. 嘔吐物に異物が混じっている
おもちゃや紐、植物の一部などが吐き出された場合、誤飲の可能性があります。異物が腸に詰まると命に関わることもあるため、すぐに動物病院へ。
嘔吐に関係する病気の一例
以下のような病気が、猫の嘔吐に関係している可能性があります。
- 胃腸炎:細菌やウイルス、異物の摂取などで起こります。
- 腎臓病:老猫に多く見られ、嘔吐、食欲不振、体重減少などの症状が出ます。
- 肝臓病:肝臓の機能が低下すると、消化機能にも影響が出て、嘔吐の症状が現れることがあります。
- 糖尿病:血糖値の変動によって、嘔吐が起こる場合があります。
- 甲状腺機能亢進症:特に高齢の猫で見られるホルモンの病気で、吐く、よく食べるのに痩せる、興奮しやすいなどの症状が出ます。
飼い主にできること
猫が吐いたとき、飼い主としてできる対応を以下にまとめます。
● 嘔吐の記録をとる
何を・いつ・どれくらい吐いたのか、どのような様子だったのかを記録しておくと、獣医師に相談する際に非常に役立ちます。
● 食事と生活環境の見直し
早食いや毛玉などの物理的な原因であれば、食器や食事の与え方を見直すことで改善するケースもあります。
● 異物の誤飲に注意
猫は好奇心が強く、口にしてはいけないものを誤って飲み込んでしまうこともあります。室内の危険物は猫の手の届かない場所にしまいましょう。
まとめ
猫が吐くという行為は、必ずしも病気のサインではありませんが、頻度や内容、吐いた後の様子によっては注意が必要です。毛玉や早食い、空腹などによる嘔吐は比較的よく見られますが、異常な嘔吐が続く場合は、何らかの疾患が隠れている可能性があります。
愛猫の健康を守るためには、日頃から様子をよく観察し、いつもと違う行動が見られたらすぐに対応することが大切です。少しでも不安な点がある場合は、早めに動物病院で診てもらいましょう。